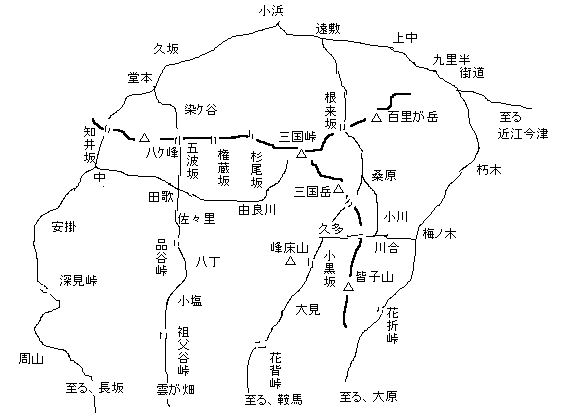 |
亙偙偺暥復偼丄僂僃僽儅僈僕儞乽嶳偺偼側偟乿乮04崋2000:02:20姧乯偵搳峞f嵹偝傟偨傕偺偱偡亜
丂
乽暥壔堚嶻偲偟偰偺嫗搒杒嶳偺摶摴乿
丂
乣俁侽悢擭偺帪傪宱偰憐偆偙偲乣
丂
丂巹偼嫗搒巗撪壓嫗嬫偺壓挰偱惗傑傟丄堢偭偨丅崱偼愓宍傕側偔側偭偰偟傑偭偨幚壠偼慶晝偺帪戙偐傜慘搾傪傗偭偰偒偨偺偩偑丄搒巗偺僪乕僫僣壔尰徾偲偲傕偵挰偼嬻摯壔丒悐戅壔偺摴傪扝傝丄傑偨慘搾偺宱塩傕惉傝棫偨側偔側偭偰偄偭偨丅
丂搶嫗僆儕儞僺僢僋偑奐嵜偝傟丄偁偺強摼攞憹寁夋偵戙昞偝傟傞宱嵪暅嫽偑愨捀婜傪寎偊偮偮偁傞徍榓係侽擭乮侾俋俇俆乯崰丄拞妛峑偵捠偭偰偄偨巹偼丄嶳妜晹偵惾傪抲偄偰巗撪偐傜杒偵朷傔傞嫗搒杒嶳傪拞怱偲偟偰丄搶嶳嶰廫榋曯偱桳柤側楈曯斾塨嶳傪昅摢偲偟偨搶嶳楢曯丄惣嶳丄斾椙嶳宯側偳傪嬱偗弰偭偰偄偨傕偺偩丅
丂嶳妜晹擖晹偺摦婡偼丄椉恊偑偄偢傟傕帺慠朙偐側嶳懞偺弌恎偲偄偆偙偲傕庤揱偭偰丄彫妛惗偺崰側偳偵偼巓偲怱懸偪偵偟偰偄偨壞媥傒偺乽揷幧曢傜偟乿偱偺帺慠懱尡偵嫆傞偲偙傠偑戝偱偁傞丅巹偺摼堄偺將憕偒塲朄偼丄曣偺幚壠偺偁傞嶰廳導徏嶃巗偺峹奜傪棳傟傞孂揷愳偺拞棳偱怺傒偵懌傪庢傜傟偰棳偝傟嬨巰偵堦惗傪摼偨偲偒偺崅壙側戙彏偱偁傞丅傑偨丄崱傕庯枴偲偟偰晝偐傜巹傊丄巹偐傜懅巕傊偲堷偒宲偄偱偄傞宬棳掁傝傕丄晝偺幚壠偺偁偭偨愇愳導偺戝惞帥愳巟棳偱偺塉奮傪掁塧偲偟偨彮擭偺崰偺僂僌僀掁傝偑崻掙偵偁傞丅埣傪撍偔愊傕傝偺儎僗傪帺暘偺旼摢偵撍偒棫偰偰捝偄栚偵憳偭偨偙偲傕夰偐偟偄巚偄弌偲偟偰僙僺傾怓偺屆傃偨幨恀偺傛偆偵婰壇偺曅嬿偵巆偭偰偄傞丅巭寣偵儓儌僊傪偡傝偮傇偟偰巊偆偙偲傕偙偺帪偺揷幧偺偨偔傑偟偄愭攜偐傜嫵傢偭偨丅
丂巹偵偲偭偰帺慠偺拞偱偺梀傃偼丄壗偵傕傑偝傞惗偒偨嫵壢彂偱偁偭偨丅
丂拞妛俀擭惗偺偲偒偺弶扨撈峴丄嫗搒杒嶳乮埲壓丄杒嶳偲棯偡乯傊偺侾攽嶳峴偼丄斞岽偲屌宍擱椏傪僉僗儕儞僌僓僢僋偵媗傔丄僥儞僩偺懼傝偵億儞僠儑僂傪嶰妏偵挘偭偰偺栰廻偱丄巹偵偲偭偰偼朰傟傜傟側偄惉挿夁掱偱偺懱尡偩偭偨丅崱偵偟偰憐偊偽丄愥偑崀偭偰傕晄巚媍偺側偄侾侾寧偺弶搤偺杒嶳偼丄掅嶳偲偄偊偳傕檢偲偟偰尩偟偔丄懱椡丒媄弍偺枹弉偝偐傜摴偵柪偭偰僶僥愗偭偨巹傪寎偊偰偔傟偨丅廔僶僗偵忔傝抶傟偰僩儃僩儃偲曢傟峴偔椦摴傪曕偄偰偄偨巹傪乽孎偵堷偐傟傞偱丅杔丄傛偆傂偲傝偱堦斢丄嶳偱攽傑偭偰偒偨傕傫傗側偁乿偲曫傟偮偮傕挰傑偱憲傝撏偗偰壓偝偭偨抧尦偺恊愗側椦嬈壠偺壏偐偄恖忣偵傕怗傟傞偙偲偑弌棃偨丅
丂旤偟偄宬棳偺憱傞愮儊乕僩儖懌傜偢偺扥攇崅尨傊楢側傞杒嶳偼丄傑偨丄墦偔偼撧椙傗嫗搒偲庒嫹傪宷偖婱廳側嶳堟偱偁傝丄懡偔偺楌巎傗暥壔傪堢傫偱偒偨偺偱偁傞丅
丂巹偺戝妛嶳妜晹帪戙偵偼丄嫞媄嶳峴偲偟偰丄傑偨壞嶳傊偺嫮壔僩儗乕僯儞僌偲偟偰丄嫗搒偺杒嬫偵偁傞巹偺曣峑丄樑嫵戝妛偐傜搆曕偱庒嫹傑偱乽嫗偼墦偰傕廫敧棦乿偲屆偔偐傜偄傢傟傞庒嫹墇偊丄嶪奨摴偺嶳摴傪嬱偗敳偗傞嵜偟偑峆椺偱丄搚梛擔偺屵屻係帪偵戝妛偺僌儔儞僪傪弌敪丅嶲壛幰偑帺桼偵愝掕偡傞俇侽僉儘傪墇偊傞嶳摴偺僐乕僗傪丄栭傪揙偟偰曕偒捠偟偰乮奺帺俀乣俁帪娫偺媥宔傪寭偹偨壖柊偼庢傞傛偆偩偑乯丄傎傏慡堳偑擔偵從偗偨尦婥側徫婄偱乮偁傞傕偺偼僽僩偵怘傢傟偰婄傪庮傜偟偰乯丄師偺擔偺擔梛擔偵偼媽崙揝嶳堿慄傪巊偭偰嫗搒傊栠偭偰棃傞偺偱偁傞丅
丂嬤擭偼丄嶪奨摴儅儔僜儞偲偄偆僂儖僩儔儅儔僜儞戝夛偑嵜偝傟偰偄偰丄媽奨摴偺杮摴傪傎傏拤幚偵堦擔偱嶳摴傪嬱偗敳偗傞偲偄偆傕偺偱丄僣儚儌僲懙偄偺嶲壛幰偑懡悢姰憱傪壥偨偟偰偄傞丅
丂巹偺庒偐傝偟崰偺杒嶳嶳峴偺僶僀僽儖丄屘怷杮師抝巵偺挊彂乽嫗搒杒嶳偲扥攇崅尨乿偵傕丄嫗偵帄傞嶪奨摴丄屲攇扟墇偺嵟抁儖乕僩偲丄戝惓偺崰傑偱庒嫹偺暷傗埣偑偙傟傜偺摶傪墇偊偰庒嫹偐傜扥攇偵撏偗傜傟偰偄偨偙偲偲傪巜揈偝傟偰偄傞丅
丂媽奨摴偺杮摴偼丄尰嵼偺崙摴俁俇俈崋慄偲偼暿偵丄埰攏岥乮尰嵼偺塆娵埰攏岥乯傪婲揰偲偟丄怺揇働抮乮傒偧傠偑偄偗乯丒巹偺帺戭偺偁傞擇尙拑壆傪宱桼偡傞丄埰攏嶲寃偺埰攏奨摴偐傜旜墇乣敧挌暯乣媣懡乮偙偺曈傝偼旡攊屛偵拲偖埨撥愳偺尮棳堟偱巹偺僥儞僇儔掁偺僼傿乕儖僪偱偁傞乯偲杒嶳傪捠傝丄峕廈偺彫愳墇乮偙偑傢偛偊乯偐傜丄崻棃嶁乮偹偛傝偞偐乯傪宱偰丄撧椙搶戝帥擇寧摪傊偺乽偍悈憲傝乿偱桳柤側恄媨帥偺偁傞墦晘乮偍偵傘偆乯傊帄傞儖乕僩偱偁傞丅傑偨丄偙偺儖乕僩偼丄擔杮偵弶傔偰徾偑懌棙彨孯傊偺專忋昳偲偟偰撿崙偐傜搉棃偟嫗傊曕偄偨偲傕尵傢傟偰偄傞丅
丂偙偺崻棃嶁偼暿柤丄恓敤墇偲傕屇偽傟丄忋悪尓怣偑搒偺嬤偔傑偱孯傪恑傔側偑傜丄偙偺嶁傪屻偵丄墇屻偵堷偒曉偟偨偺偱偁傞丅傑偨丄尦婽尦擭乮侾俆俈侽乯偺挬憅峌傔偱棤奨摴傪攕憱偡傞憤戝彨怣挿傪僇儌僼儔乕僕儏偟偰丄廏媑偲壠峃傕偙偺恓敤墇偺杮奨摴傪彫愳墇偐傜媣懡丄彫崟嶁丄敧挌暯傪宱偰嫗傊摝偘婣偭偨偺偱偁傞丅
丂傑偨丄偙偺奨摴偺搑拞偵偁傞悪摶偐傜偺戝尒旜崻偼丄恗暯係擭乮侾侾俆係乯憂愝偺暯壠墢偺廋尡摴偺帥丄戝斶嶳曯掕帥傊偺嶲寃摴偵傕巊傢傟偰偄偨楌巎偺屆偄摴偱偁傞丅暯惔惙傕庒擭偺崰偵偙偺曯掕帥寶棫偺嶨彾乮岺帠娔撀乯傪嬑傔偨偙偲側偳偼丄摿昅偵抣偡傞傕偺偱丄偁偺惔惙傕庒偒擔偵埰攏奨摴傪婔搙偲側偔曕偄偰偄偨偺偱偁傞丅扐偟丄惔惙偑曕偄偨偺偼丄悪摶乣戝尒旜崻乣僠僙儘扟乣敧瀍墇乮傗傑偡偛偊乯乣戝斶嶳偺儖乕僩偱偁傝丄敧瀍墇偼崱偱偼攑摴偲壔偟偰偟傑偭偨丅
丂堦曽丄嫗偺幍岥偺堦偮挿嶁岥傪弌敪揰偲偟偰丄嫗尒摶偐傜悪嶁乣拑撣摶傪墇偊偰嶳崙偵帄傞丄扥攇楬偺挿嶁墇乮堦柤丄嶳崙墇乯傕偐偭偰偺姴慄儖乕僩偲偟偰丄屆偄楌巎傪帩偭偰偄傞丅懢暯婰偵乽摴柧挿嶁傪宱偰墇慜傊棊偪峴偔乿偲婰偝傟丅墑尦俁擭乮侾俁俁俇乯怴揷媊掑傜偺孯惃偑嫗傊峌傔擖傠偆偲偟偨偲偒乽偦偺惃俁侽侽梋婻丄敀拫偵嫗拞傪懪捠偭偰丄挿嶁偵懪偪忋傞乿偲傕婰偝傟偰偄傞丅
丂庒嫹偱堦墫偝傟偨嶪偑揤攭朹偵扴偑傟栭傪揙偟偰廫敧棦乮俈俀嘸乯偺摴偺傝傪嬱偗偰嫗傊撈摿偺晽枴偲側偭偰撏偗傜傟偨偺偱偁傞丅
丂嫗偺嵳偵偮偒傕偺偺嶪偺巔庻巌偼丄巹傕戝偺岲暔偩偑丄偙偺庒嫹偺嶪偲杒慜慏偑偼傞偐壼埼偺抧偐傜塣傫偩棙怟崺晍乮僶僢僥儔乯偲峕廈暷偲偄偆栶幰偑懙偭偰丄擇昐悢廫擭偲偄偆帪傪宱偨崱傕嫗偺枴偺暥壔傪忴偟弌偟偰偄傞偺偱偁傞丅
丂抰嫹峫乮傢偐偝偙偆乯偲偄偆峕屗枛婜偺彂暔偵丄彫昹偐傜嫗傊峴偔摴偼嶰偮偁傞偲偟偰丄(1)扥攇敧尨捠乣廃嶳乣挿嶁乣戦曯丄(2)廰扟乮愼偑扟亖屲攇扟墇偊乯乣媩嶍丒嶳崙丄(3)墦晘乣崻棃乣媣揷乮媣懡乯乣埰攏丄偺儖乕僩傪婰偝傟偰偄傞丅
丂尰嵼偺塤偑敤傊偺愳増偄偺摴傕栺侾俇侽擭慜偺暥惌擭娫偵奐偐傟偰偍傝丄塤偑敤奨摴偺墑挿偲偟偰偺庒嫹奨摴乮忋夑栁乣塤偑敤乣堜屗乣彫墫乣敧挌乣嵅乆棦乣屲攇扟墇乯傕偦偺愄偼旜嶸晘乮偍偝偠偒乯偲偄偭偰丄栻巘摶偐傜嶸晘妜偺旜崻傪捠傝丄愇暓傪宱偰堜屗慶晝扟偐傜堜屗偵払偟偰偄偨丅傑偨丄崅栰偐傜戝尨偺愳増偄偺摴傕埲慜偵偼斾塨嶳懁偺斾妑揑崅偄偲偙傠傪僩儔僶乕僗婥枴偵捠偭偰偄偨傕偺偑嶰杮偔傜偄妋擣偱偒傞偦偆偱丄帪戙偲偲傕偵壓偺摴傪棙梡偟偨傜偟偄丅偦偺愄偵嫗偐傜戝尨傊帄傞摴傕暯壠暔岅偵岅傜傟傞暥帯俀擭乮侾侾俉俇乯偺屻敀壨朄峜偑庘岝堾偵寶楃栧堾傪朘偹傞戝尨屼岾乮偍偍偼傜偛偙偆乯偺摴偱偁傞忋夑栁乣擇尙拑壆乣惷尨乣峕暥摶乣戝尨偑巊傢傟偰棃偨偺偱偁傞丅
丂柧帯係侽擭丄尰嵼偺幵摴偑壴攚摶傪墇偊傞偵帄偭偰丄媽摶偲柤傪曄偊傞偙偲偲側偭偨尰嵼偺壴攚媽摶丄戝尒旜崻偺悪摶丄擖傝岥偵偍抧錟條偺偁傞僼僕扟摶丄敧挌暯偺媣懡懁傊偺彫崟嶁乮僆僌儘僒僇乯側偳偼丄崱傕悪偺屆栘傗媭偪壥偰偨愇奯摍偲偲傕偵楌巎偺廳傒傪崱偵揱偊偰偄傞丅摿偵丄偐偭偰敧挌暯偵偼榋広摴偲偄傢傟傞棫攈側摴偑捠偭偰偄偨偲偄偄丄偦偺柺塭傪巆偡屆摴偼丄崱傕幖尨偺搶懁傪傑偔傛偆偵懕偄偰偄傞丅敧挌暯傊偺暿偺擖傝岥偵偁偨傞僼僲嶁偼丄嬤擭偵奐偐傟偨摴偱丄杮摴偼丄嶰廫嶰嬋嶁偲偄傢傟傞乮垽搯孲懞帍丗柧帯係係擭姧乯彫崟嶁偐傜敧挌暯偺搶懁傪宱偰僼僕扟摶傪捠偭偨偺偱偁傞丅僼僕扟摶摴傕彫崟嶁偲摨條偵偮偯傜愜傟偺摶摴偱偁傝嶪奨摴偲偟偰偺嫟捠揰偑姶偠傜傟傞丅
丂巹偑妛惗帪戙偵墇偊偨庒嫹墇偺奨摴偼丄惣偐傜丄敧曯嶳偺抦堜嶁丄屲攇扟丄悪旜嶁丄偲昐棦偑妜偺崻棃嶁側偳偱偁傞丅
丂偙偺傛偆偵梱偐偄偵偟偊偺楌巎傪堢傫偩杒嶳傪條乆側憐偄傪傔偖傜偣側偑傜丄巕嫙偺崰偐傜曕偒懕偗偰棃傞偙偲偑弌棃偨偙偲偼丄巹偵偲偭偰戝偒側嵿嶻偱偁傝丄壗暔偵傕懼偊擄偄岾偣偱偁偭偨丅
丂崱偱偼屲攇扟偵偼椦摴偑捠偭偰丄偐偭偰帺暘偺懌偱墇偊偨丄戂傓偟怺偔摜傒崬傑傟偨屆摴偼攑摴偲壔偟桏偵杽傕傟偰偟傑偭偨丅
丂崻棃嶁傕壓敿暘偼椦摴偵嶍傜傟偰偟傑偭偰丄崱傑偨怴偨側椦摴奐敪偑楌巎揑堚嶻偲傕尵偊傞偙偺媽奨摴傪峏偵愗傝崗傕偆偲偟偰偄傞偺偱偁傞丅
丂乽摴偲偼幮夛揑崌堄偺寢懇偱偁傞乿偲幮夛妛揑偵掕媊偟偨恖偑偄傞偑丄偁傞幰偼揤攭朹傪扴偓丄偁傞帪偼攕憱偺晲彨偑偲偄偆傛偆偵丄堊惌幰傕弾柉傕偦傟偧傟偺巚偄偱捠偭偨婱廳側暥壔揑懌愓傪寢懇偟偰崗傒崬傫偱棃偨偺偱偁傞丅
丂杒嶳偺旜悾偲徧偝傟傞婱廳側崅憌幖尨偺偁傞敧挌暯傕椦摴奐捠偺婋婡偵嶯偝傟偨偑丄嶳妜楢柨傗帺慠垽岲壠偺曽乆偺搘椡偱恏偆偠偰儖乕僩曄峏偲側偭偨偑丄偙偺奐敪偺塭嬁偱僼僕扟摶傕摶偺偡偖嬤偔傪丄傑偨彫崟嶁傕壓敿暘偼柍巆偵椦摴偵嶍傜傟偨傑傑丄儖乕僩曄峏偱曻抲偝傟偨丅僼僕扟摶側偳偼傾儅僑掁偵摶傪墇偊偰峕夑扟嵍枔偺悈宯偵擖傞偲婫愡偵偼儎儅儃僂僔偺恀偭愒側幚偑傆傫偩傫偵庢傟偨傕偺偱丄僈僒僈僒偲栰揺偑旘傃弌偟偨傝偟偰嬃偐偝傟偨傝偟偨傕偺偩偑丄崱偼尒傞塭傕柍偔側偰偟傑偭偨丅
丂偙偺杒嶳偲偄偆丄帺慠偲暥壔偺傆傫偩傫偵惙傝崬傑傟偨丄楌巎堚嶻偱傕偁傞桏嶳偼丄傑偨丄婔懡偺傾儖僺僯僗僩傪僸儅儔儎偵憲傝偩偟丄朘傟傞幰傪桪偟偔曪傒崬傫偱偔傟偨傕偺偩丅挰偺嶨摜傪棧傟偰丄偙偺桏嶳偵暘偗擖傟偽丄恎傕怱傕惔傔傜傟傞巚偄偑偟偨傕偺偱偁偭偨丅
丂偐偭偰偼丄杒嶳偵摶摴傪扵偟媮傔偰偺嶳峴偵偼丄憡摉偺撉恾擻椡傪梫媮偝傟偨偟丄扟偺巟棳傪傂偲偮摜傒娫堘偊傟偽堦擔偺嶳峴傪朹偵怳偭偰丄扟増偄偵廤棊傑偱偺壓崀傪梋媀側偔偝傟偨乮摴偵柪偭偨帪偼扟傪壓傞偲偄偆嶳偱偺儖乕儖堘斀偼丄棽婲弴暯尨偲偄偆戧傕杦偳側偄杒嶳偺傒偵嫋偝傟傞忢幆偲偟偰拞妛嶳妜晹偺屭栤偺愭惗偐傜傕尵偄暦偐偝傟偰偒偨乯丅栜榑丄摴昗傕彮側偄懼傝偵僑儈側偳偼尒妡偗傞偙偲傕側偐偭偨丅
丂巹偑崅峑惗偺偲偒偺徍榓係俁擭乮1968乯埲崀丄庒嫹偺尨巕椡敪揹強偐傜娭惣揹椡偵傛偭偰俆侽枩儃儖僩偺揹椡傪嫗嶃恄偵嫙媼偡傞偨傔偵愝抲偝傟偨憲揹慄偲崅埑揝搩偼丄杒嶳偵怓乆側堄枴偱偺戝偒側僟儊乕僕傪梌偊傞寢壥偲側傞丅
丂傑偨丄恖椡偱栘嵽傪斃弌偡傞堊偺栘攏摴乮偒傫傑傒偪乯傕杒嶳偺晽暔帊偲傕偄傢傟偨偑丄偙傟偵庢偭偰戙傢偭偨儚僀儎乕幃偺嵽栘斃弌曽幃偐傜丄峏偵愜傝偐傜偺崙嶻椦嬈偺晄嫷傕庤揱偭偰宱嵪岠棪傪捛媮偡傞偨傔偺椦摴奐敪偼丄扟偺帄傞偲偙傠偵戝偒側捾嵀傪棫偰傞寢壥偲側偭偨丅
丂杒嶳偺扟嬝傪栘攏摴傪扝偭偰嵟尮棳偵帄傟偽丄傢偢偐偵堦書偊偔傜偄偺彫億僀儞僩偵椙宆偺傾儅僑偺晇晈偑梀塲偡傞條巕偵弌偔傢偡偙偲傕偟偽偟偽偱偁偭偨丅偙偺扟偺曮愇偲傕歡傜傟傞宬棳嫑傕崱偱偼杮摉偵彮側偔側偭偰偟傑偭偨丅
丂宬棳掁偱偼丄娐嫬攋夡偺嶰埆偲偟偰丄椦摴丒敯嵦丒墎掔偑尵傢傟偰偒偨偑丄杒嶳傕娐嫬攋夡偺椺奜偲偼側傝偊側偐偭偨偺偱偁傞丅
丂偦偟偰丄崱丄傑偨杒嶳偼扥攇峀堟婎姴椦摴奐敪偲偄偆岞嫟帠嬈偵柤傪庁傝偨栚揑偺晄柧妋側寁夋偺慜偵峏偵抳柦揑側僟儊乕僕傪庴偗傞婋婡偵嶯偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅
丂奐敪偝傟偨椦摴傪墱傑偱係WD偱擖傝崬傫偱偔傞恖偨偪偵傛偭偰嬻娛傗僒儈僢僩僶僢僋偵擖偭偨傑傑偺僑儈偑曻抲偝傟丄嶳彫壆偺偁傞杒嶳偺扟偲偟偰慜弎偺乽嫗搒杒嶳偲扥攇崅尨乿偵傕徯夘偝傟偨栘攏摴偺懕偔旤偟偐偭偨宬扟傕崱偼尒傞塭傕側偄丅
丂戝検惗嶻丒戝検徚旓丒戝検攑婞偲偄偆暔幙桪愭偺幮夛偼傑傞偱恖乆偺怱傑偱昻偟偔偟偰偟傑偭偨偐偺傛偆偵偝偊巚傢傟傞丅
丂巹偼嶪奨摴偺堦偮偺摶摴偱偁傝丄峕屗偐傜柧帯偺崰傑偱丄摶偵拑壆傑偱偁偭偰乽僆僞僱偝傫乿偲偄偆彈惈偑峴偒棃偡傞峴彜恖偨偪偺愙懸傪偟偨偲偄傢傟傞乽扥攇墇乿偲偄偆摶摴傪挷傋偰偄傞丅嬐偐悢廫擭偲偄偆娫偵柉廜偺乽幮夛揑崌堄偺寢懇乿偑帪戙偺挭棳偺拞偵杽傕傟偰偄偭偰強嵼偝偊晄柧偲側偭偰偄傞偺偱偁傞丅
丂懠曽丄強嵼偑尰嵼傕柧妋偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄偦偺楌巎丒暥壔揑壙抣傛傝傕宱嵪傪戝帠偲偡傞怱偺昻偟偝偵屘偵攋夡偝傟偰偄偔愭恖偑巆偟偰偒偨偙傟傜偺婱廳側暥壔揑懌愓傪巹偼孞傝曉偟傗傝偒傟側偄婥帩偪偱尒憲偭偰偒偨偺偱偁傞丅
丂帺慠傕傑偨婱廳側愭恖偐傜巕懛傊庣傝揱偊偰偄偔傋偒堚嶻偲掕媊偡傟偽丄偦偺堚嶻乮帒杮乯偺尦嬥偵庤傪偮偗傞偙偲側偔丄偦偙偐傜嶻傒弌偝傟傞棙懅傪忋庤偵妶梡偟偰偦偺壙抣傪嫕庴偟偰偄偔傛偆側弞娐宆偱帩懕壜擻側塣梡偑壗屘恾偭偰偄偗側偄偺偐丅
丂偐偭偰丄巹偺惗傑傟偨徍榓俀俇擭偺崰偵旜悾偑愴屻偺宱嵪暅嫽傊偺揹椡嫙媼偺偨傔偵僟儉偺掙偵捑傔傜傟傛偆偲偟偨丅摉帪偺帪戙攚宨偺側偐丄乽揹婥偐僩儞儃偐乿偳偪傜傪偲傞偺偐偲慖戰傪敆傜傟偨偲偒丄乽NO乿偲惡傪忋偘偨愭恖払偺抭宐偲桬婥偁傞峴摦偵丄巹偨偪偼丄偄傑妛傇傋偒帪偱偼側偄偩傠偆偐丅
晅榐丗
|
|
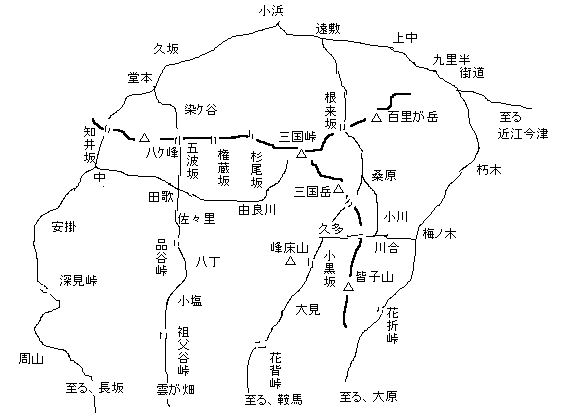 |
亙偙偺暥復偼丄僂僃僽儅僈僕儞乽嶳偺偼側偟乿乮04崋2000:02:20姧乯偵搳峞f嵹偝傟偨傕偺偱偡亜