よも山ばなし(投稿)
遥かなる若狭越2
(大砲も越えた知井坂)
〜知井坂
(チイサカ)の名の由来〜応永
15年(1408)6月、日本で最初にゾウが若狭小浜に上陸し、若狭越をして京まで歩いた前回の話に続き、今回は大砲が京都から若狭に越えた知井坂の話をしてみたい。若狭遠敷郡誌(大正
11年刊:遠敷郡教育会編)によれば、「..南川流域に属する名田庄方面より丹波に出て又大飯郡に通じ若狭湾と京阪との捷路をなしたるもの数条あり、これを図示すれば左の如し」とし、下図のように、小浜から、南川流域の街道に、納田終、坂本、堂本、上根来の4コースを示している。また、堂本からは更に血坂越(知井坂)と五波谷越を、最短コースとして上根来・針畑越をそれぞれ示している。ゾウが越えたと言われるのは針畑越で、大砲が越えたのは堂本コースの一つ知井坂である。
血坂越ともいわれるこの峠の呼び名の由来には、昔からこの峠越えは険峻であったためこれを越えるのに血涙を流すほど苦しんだことからとするものと、その昔、この峠を境にして激しい土地争いの戦
(いくさ)があり、道に倒れた戦士達の血で赤く染まったことから血坂とする二通りの説がある。前者は「若狭郡県誌」、後者は「北桑田郡誌」の所載である。知井坂は古くは知坂(血坂:チサカ)といい、「チ」とは古代の道(すなわち街道)の意とも、「茅」すなわちススキの生い茂ったチガヤの意であるとも言われる。いずれにしてもこの坂の命名への確証には至らない。
〜越えたのは、山砲?それとも野砲?〜
故森本次男氏の「京都北山と丹波高原」の知井坂の項に大砲の通った峠と題して、「数多くの山旅人がこの峠で日本海に別れをつげたり、同じ海へ越えてゆく希望で望んだことであろう。たまに魚屋さんが通る、という言葉は知見でも聞いた。そしてその時に、今でも通れないことはあるまい、とにかく戦前には兵隊が大砲をひいて越えたくらいだから、という言葉も聞いたのであった。大砲というのは野砲か山砲か、多分は山砲であろう」と紹介されており、峠を越えた大砲を分解可能で機動力のある山砲との合理的想定を示しておられる。
しかし実際に峠を越えたのは旧陸軍京都師団の野砲であった。「本村と丹波知井村矢原との通路にして堂本より坂路約二里にして峠なり。去る明治
43年10月深草輜重隊(しちょうたい:野砲隊)の馬をひき車をとおして此処を通過したることのあれば難渋にてはあらんも金剛杖の必要までには至らず。さればにや数貫の重荷を肩にあるいは背にして丹波に若狭に行きかふ人の楽々しく見ゆる。何故に血坂の名の起こりしかを怪ましむるばかりなり」と「知三村誌」(大正4年刊)からの引用が「知井村史」(平成10年刊)に記され、血涙説に否定的見解も示している。北山クラブの故金久昌業氏は「北桑田郡誌」からの引用として、大砲が通った年を「明治
34年10月」と記されている。いずれが正しいか確かめてはいないが、いずれかが年数を取り違えたものと思う。大正
5年生まれで、中国大陸に旧陸軍、山砲二番砲士として従軍した私の父の話によれば、「野砲も山砲も口径は75mm(握りこぶし大)で、山砲は分解して6頭の馬の背に、更に弾薬を5頭の馬の背に、計11頭の馬で編成。射程距離は八千メートル(実際には一万メートルはゆうに飛んだ)で、機動力を誇った。山砲の総重量は約六百キロであった(山砲は、94式といい、旧式の明治41年製の41式を昭和9年4月に改良したもの)。一方、野砲は分解できず(山砲と同様の41式)、砲身の厚さも大で、恐らく一トン近い重量があったろう。馬で引く場合は、最低でも3頭以上を連ねたものと思う。また、相当の道幅がないと通れない」とのことであり、「六尺もあれば問題なく通れたろう」とも語ってくれた。当時の間道が四から五尺(1.2〜1.5メートル)といわれ、本道は最短コースの針畑越が馬も(ゾウも)通れる六尺道として北山の高層湿原、八丁平にその痕跡を残している。相当に整備された街道が幾筋も京に続いていたのである。旧陸軍と言えば、「私たちに残した唯一有益なものは五万図のみ」といわれ、私が中学山岳部に所属していた昭和
30年代、「北山からヒマラヤまで」を合い言葉に北山を歩いていた頃には、この三角測量のやや正確さを欠く五万図を頼りに薮を漕ぎよく道に迷ったことも今では懐かしい想い出である。
〜あの蓮如さんも越えた〜
旧陸軍はまた、昭和
8年の記録的大雪の前年にあたる昭和7年(1932)1月17日に福知山連隊約五百名が知井坂越雪中行軍を行なっている。あの「八甲田山」のような訓練がここでも行なわれた。次の年のことでなくてよかったものだ。また、はるか古(いにしえ)に溯れば、あの蓮如上人も北陸の教化ののち、文明
7年(1475)、小浜から知井坂を越え丹波路を経て摂津に向かい、やがて山科に本願寺を建てるが、知井村でも盛んに布教したのである。南北朝時代の至徳2年(
1385)建立と伝えられる石塔が知井坂の峠部分を形成する八ケ峰(ハチガミネ)の山頂付近に有る。「国境に石碑あり、新田義貞の建立せしものなり。その真否を確かむる記録なしを惜しむ」(知三村誌)としているが、義貞の没年(1338)とは符合しない。私が昭和
40年頃に越えたときには、残念ながらこの石塔を確認していないが、鉢を伏せたような草原状の山頂に暫し休憩した。陽の当たる気持ちの良いひととき、現れでた野兎は青い若狭湾を背にそのレーダーのような耳をそば立てて私たちに注意を傾けていた。この八ケ峰は、鉢を伏せたようなその形状から名を取っているとも、また、八ケ国(丹波、丹後、但馬、山城、近江、越前、加賀、能登)が見渡せるところから由来しているとも言われ、ここでも説が分れる。
この山頂にある高さ
40センチ位の石塔は、蓮如さんも、馬に引かれた大砲も、行き交う行商人たちも、またときには雪の下から大勢の兵隊が雪中行軍するのも、六百年以上に亘ってどのような気持ちで、これらの往来を見守り続けてきたものであろうか。
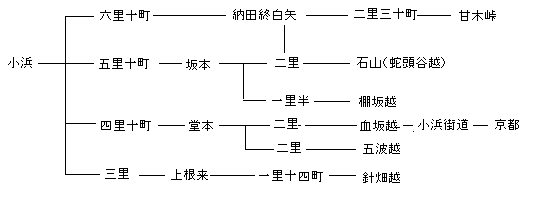
<参考文献>
「京の北山ものがたり」斎藤清明著
(京都文庫2、松籟社:平成5年刊)
「京都北山」北川裕久著
(岳洋社:昭和
60年刊)「京都北山と丹波高原」森本次男著
(山と渓谷社アルパインガイド:昭
和
34年刊)「北山の峠」(中)金久昌業著
(ナカニシヤ出版:昭和
54年刊)「京都北部の山々」金久昌業著
(創元社:昭和
48年刊)「京都北山を歩く3」澤潔著
(ナカニシヤ出版:平成
4年刊)「京都美山
知井村史」知井村史編集委員会編(平成10年刊)